


 |
| 電動車椅子に乗って撮影中の大重監督 |


 |
| 追い込み漁アンティギャーにおける魚の分配 |
 |
| 佐藤善五郎さんと研究会若手メンバー |
| ・ | 上野和男(1996)「波照間島の祖先祭祀と農耕儀礼―ムシャーマ行事を中心とする盆行事の考察―」国立歴史民俗博物館研究報告.第66集.179-200頁. |
| ・ | 沖縄映像文化研究所(2005-)「久高オデッセイ」大重潤一郎監督、須藤義人助監督作品. |
| ・ | 北村皆雄(2006)「秘儀を撮る・撮らない:沖縄西表島古見、アカマタ・クロマタの祭祀」北村皆雄、川瀬慈、新井一寛編著『見る、撮る、魅せるアジア・アフリカ!―映像人類学の新地平―』新宿書房.144-182頁. |
| ・ | 高良 勉(2005)「沖縄生活誌」岩波新書. |
| ・ | 民族文化映像研究所 (1988)「まちゃん−待網漁−」12分、姫田忠義監督作品. |

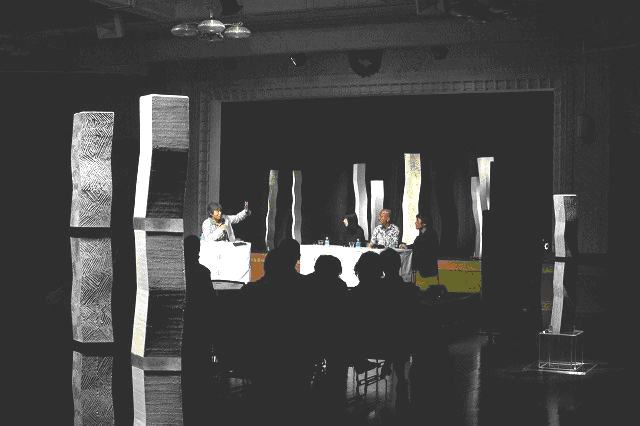


「あなたがどんなことにこころを向けるにせよ、音楽はその面での才能を高めてくれるだろう。そして感知できないはたらきにより、しかし感覚でとらえ得る効果をもって、音楽は感性を高めるのだ。それゆえ、勇敢な人の場合は勇気が、敬虔な人の場合は信心が護られ高められる。それでアイルランドの司教や修道院長、聖人はどこへ行くにもハープを携え、敬虔な気持ちでそれを奏でて楽しむのを常とする。かくて聖ケイヴィヌスのハープは今日までこの国の者に大いに崇拝され、功徳をもたらす偉大な聖遺物と考えられている」(p. 209)。「聖人の島」とも呼ばれるアイルランドの国家紋章として竪琴が選ばれた背景の一端が伺われる記述です。またギラルドゥスはカシオドルス(Flavius Magnus Aurelius Cassiodorus、ローマの政治家・著述家)がハープのもたらす利について述べていることを引用しています。
「有毒な苦悩をのぞいて楽しくする。ふくらんだ怒りを鎮める。残酷な粗暴さを礼儀にかなったものにする。怠惰を抑制する。無気力さから人を目覚めさせる。徹夜をする者に有益な休息をあたえる。みにくい欲望に埋められた貞潔さを気高い愛へとよびもどす。よい考えから常に人を遠ざける倦怠感を癒す。有害な嫌悪感を有用な感謝の念に変える。そして癒しをもたらすもっともすぐれた手段として、ごく甘い楽しみでこころから激情を排する。かたちのないこころをかたちあるもののようになでさする。そして聴覚のみでそれを望む状態へともたらす。黙っていても、ことばでやわらかく伝えられないことを手で言いあらわし、口を使わずに述べる。そして感知できないものを従えることによって感覚を支配することができる。神のあわれみはその恩恵をひろめ、その被造物すべてをおおいに称賛されるべきものとする。確かにダヴィデの琴は悪魔を追いはらった。その音は霊をあやつった。ハープを三度ひいて王は自由をとりもどした。不面目にもそれをこころの中で敵に奪われていたのだが」(pp. 212−13)。ハープに悪霊を払う呪力、病の癒しの力が認められていますが、ここで言及されているダヴィデのハープというのは、旧約聖書の「サムエルの書」(16: 14−23)にある挿話で、若き日のダヴィデがサウル王に憑いた悪霊を、竪琴の演奏で追い払ったというものです。ダヴィデが奏でた楽器‘kinnor’は、英語で‘harp’と訳されていますが、正確には ‘lyre’という古代ギリシアの弦楽器です。
「こううたって、言葉にあわせて弦をかき鳴らすと、血の気のない亡者たちも、もらい泣きした。[中略] 復讐の女神たちも、すっかり歌に感動して、はじめて、頬を涙で濡らしたということだ。王妃プロセルピナも、冥王も、オルペウスの嘆願を拒むことができないで、エウリュディケを呼び寄せた」(オウィディウス『変身物語』(下)中村善也訳、岩波文庫、1995年、pp. 61−62)。またオルペウスの竪琴の音は木々をも魅了し、彼の周りには木々が飛来し木陰をつくったといいます(p.64)。オルペウスの父はトラキア王オイアグロス(またはアポロン神)、母は文芸を司る女神ムーサイ/ミューズの一人カリオペーで、竪琴の技はアポローンから伝授されたともいいます。神々の血を引くオルペウスの竪琴の音楽には、生者のみならず死者も冥界の神々も、また樹木をも動かす神秘の力が籠っていたわけです。
‘Tair Daur Dá Bláo,竪琴には‘Daur Dá Bláo’と‘Cóir Cethairchuir’という二つの名前があり、前者は‘Oak of Two Meadows’という意味、後者は‘proper, fitting, just, true’ + ‘four-side, square’という意味だとされています。後者の名前から、このダグダの‘cruit’は四角い形状だったものと思われます。‘Oak’がドルイディズムにおいて聖なる樹であることは周知のとおりです。
Tair Cóir Cethairchuir,
Tair sam, tair gam,
Béola crot 7 bolg 7 buinne!’
(‘Come Daur Dá Bláo,
Come Cóir Cetharchair,
Come summer, come winter,
Mouths of harps and bags and pipes!’)
コナル王の美しい娘トゥアグは、タラの王宮で男たちの目にふれることなく大切に育てられていた。やがて王侯たちがトゥアグに求愛するようになると、その噂を聞き及んだ海神マナナン・マク・リルは、輝かしき肌のトゥアグを愛するようになった。マナナンは、トゥアタ・デー・ダナンのドルイド、エオガヴァルの養父であったが、このエオガヴァル息子のフェル・フィーを使者としてタラの王宮に送り込んだ。ドルイドのフェル・フィーは、女性の姿をとってトゥアグの侍女になりすまし、タラに三日間滞在する。そして四日目の晩、娘に魔法の呪文を唱えて娘をぐっすり眠らせ、肩にかつぎ「眠りの旋律」を奏でると、娘をタラから海辺へと運び去ったのである。しかし彼が舟を捜しに行っている間に、娘は波にさらわれて溺れ死んでしまう。マナナンは、娘を連れ帰って来なかったドルイドを殺してしまった。そこで、その河口(インヴェル)は「マナナンの妻」の名前、すなわちトゥアグにちなんでトゥアグ・インヴェルと呼ばれるようになったのである。エオガヴァルは、ここではトゥアタ・デー・ダナンのドルイドとなっており、その息子フェル・フィーも同様です。彼は「眠りの呪文」だけでなく「眠りの旋律」をも操っています。このテクストからも明らかなように、「眠りの呪文」と「眠りの旋律」は明らかに重複しています。これは、フェル・フィーがドルイドでありまた‘tiompán’の奏者でもあるという伝承を反映したものと思われます。またこの反復は、「眠りの呪文」と「眠りの旋律」が同質のものとして受け取られていたことを示唆しているとも考えられます。どちらも死につながる魔法の眠りをもたらす、呪詛的な性格が濃厚なものなのです。
ここで、もう一つ、「あしわけ小舟」から引用して置こう。「カナシミツヨケレバ、ヲノヅカラ、声ニ文(アヤ)アルモノ也。ソノ文ト云ハ、哭声ノ、ヲヽイヲヽイト云ニ、文アル也。コレ巧ミと云ホドノ事ニハアラネド、又自然ノミニモアラズ、ソノヲヽイヲヽイニ、文ヲツケテ、哭クニテ、心中ノ悲シミヲ、発スル事也。モトヨリ、外カラ聞ク人ノ心ニハ、ソノ悲シミ、大キニフカク感ズル也。カヤウノ事ハ、愚カナル事ノヤウナレドモ、サニ非ズ。サレバ、モロコシニテ、喪ノ時ニ哭スル礼ノ定マリタルモ、仮令(ケリャウ)ノ事ノヤウナレドモ、モト実情ヲ導クシカタ、聖人ノ智ハ、フカキモノ也」
実利実用に繋がる諸制度に慣れた人々は、礼というものをややもすれば贅物と考え易い。内容を欠いた、便宜的な、外的規制と見勝ちだが、それは浅薄な考えであって、そういう人達が「愚カナル事」「仮令ノ事」と見るところに、却って礼の本質的なものが顔を出している。(中略)
突き詰めて行けば、礼とは、「実情ヲ導ク」その「シカタ」だと彼は言う。それなら、これは言葉なき歌とも言えるわけだ。私達は、この「シカタ」を何によって思い附くのでもなく、何処から借りて来るのでもない。それは実情自体から「ヲノヅカラ」「ほころび出」る。もう少し精しく言えば、「巧ミト云ホドノ事ニハアラネド、又自然ノミニモアラズ」という具合に生れて来る、と宣長は考える。私達は、意識して自発的にそうするのでもなければ、無意識に事の成行きに従うのでもない。人間の構造は、そのような出来だ、と彼は言っていると解してよかろう。
(小林秀雄『本居宣長』岩波文庫、1992年、pp.280-281 なお、表記は横書きweb表示にあわせて、多少改めてある。雑誌掲載時に修正の予定。)